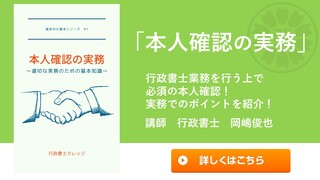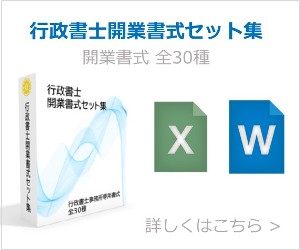この記事では、行政書士が代表的な3つの法人設立業務を効率よく学ぶために必要なことについて説明します。
法人設立業務とは
法人設立業務とは、その名の通り「法人」を設立するために必要な手続をする業務です。
法人とは、自然人以外のもので、法律上権利義務の主体となり得るものをいいます。例えば、株式会社や合名会社、合資会社、合同会社、一般社団法人、一般財団法人、非営利活動法人、社会福祉法人、医療法人、学校法人、宗教法人などです。
世の中にはこうした様々な法人が存在しますが、その中でも行政書士がよく相談や依頼を受け、設立業務で携わることが多い代表的な法人形態は、「株式会社」「合同会社」「一般社団法人」の3つとなります。
行政書士として法人設立業務に携わりたいと考えたとき、まずは「株式会社」「合同会社」「一般社団法人」の設立手続についてきちんと学び、基礎知識や業務の流れなどをおさえておくとよいでしょう。
各法人設立業務の主な特徴
①株式会社の設立業務の主な特徴
「法人」と聞いて真っ先に思い浮かべるのは、おそらく「株式会社」なのではないかと思います。
実際に、行政書士が最も多く設立の相談や依頼を受ける可能性が高い法人は「株式会社」です。
世間一般でも株式会社はメジャーな法人形態であり、何か会社を設立したり、個人事業形態から「法人成り」する際にまず考慮したりするのが株式会社なのではないかと思います。
株式会社は、「発起人」が定款を作成し、公証役場で公証人による定款の認証手続をした後、資本金の払込をして、最終的に法務局で設立登記申請を行うことで成立します。
行政書士は、主にお客様となることの多い発起人から依頼を受けて、発起人に代わって定款を作成し、公証役場で定款認証手続を行います。設立登記申請は、お客様自身で行っていただくか、又は司法書士をご紹介して対応してもらうことになります。
②合同会社の設立業務の主な特徴
合同会社は、合名会社・合資会社とともに「持分会社」と呼ばれる法人形態です。
ただ、世間一般では、「合同会社」そのものの知名度は決して高くはないと思います。
合同会社の社員が全員「間接有限責任」である点は、株式会社の株主と同様です。
ただ、株式会社に比べて設立費用やランニングコストが安く、経営の自由度が高いなどのメリットがあります。そのため、株式会社の設立について行政書士に相談したものの、合同会社のメリットを聞いて合同会社の設立に切り替える、といったこともあります。
また、合同会社の設立業務で大事なポイントの一つが「定款認証手続が不要」ということです。これは、設立までのスケジュールを短縮できるというメリットがある反面、公証役場で公証人に定款をチェックしてもらうことができないため、より注意深く定款を作り込む必要があるということでもあります。株式会社の設立以上に、定款作成の場面では行政書士の「腕の見せ所」となります。
③一般社団法人の設立業務の主な特徴
株式会社と合同会社の設立については「会社法」に規定がありますが、一般社団法人の設立については「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に規定があります。
また、株式会社と合同会社は営利を目的とする「営利法人」であるのに対し、一般社団法人は営利を目的としない「非営利法人」となります。
ただし、一般社団法人は、「非営利法人」であっても収益事業を行うことができます。
このあたりについては、非営利活動法人(NPO法人)と似ている点もありますが、一般社団法人の方が非営利活動法人よりも簡易迅速に設立することができます。
そして、一般社団法人を設立するためには、株式会社と同様に公証役場で公証人による定款認証の手続が必要です。
さらに、一般社団法人を設立するためには、「設立時社員」が2名以上必要です。
この「設立時社員」ですが、行政書士が依頼を受ける場合は人数が多くなることもよくあります。時には10名を超えることもあり、設立時社員の人数が多ければ多いほど、定款認証手続の際に必要となる書類の数も多くなりますので、行政書士としてはきちんと設立までのスケジュールを綿密に組んで、業務に遅れが生じないよう注意して進めていく必要があります。
法人設立業務の勉強
法人設立業務を行うにあたり、当然ですが最低限の知識が必要となります。最低限の知識がなければ相談対応も難しく、受任も難しくなります。
法人設立業務の学び方としては、まずは会社法に関する基本書などを読み込むといいでしょう。大学の先生などが執筆している基本書を最低1冊、可能であれば2~3冊程度読み込めば十分だと思います。
株式会社と合同会社の設立については会社法に規定がありますが、そもそも会社法に関する最低限の知識がなければ、株式会社と合同会社の定款を「プロ」として作成することは難しいでしょう。
ネット上では、定款の雛形やフォーマットなどを無料でダウンロードできるサイトもあるようです。
でも、行政書士は法人設立業務の専門家であり、お客様から報酬をいただいて業務を行う以上、「プロが作成する定款」を仕上げなければなりません。定款に必ず盛り込まなければならない「絶対的記載事項」をきちんと盛り込むことはもちろん、お客様からきちんとヒアリングをした上で、「相対的記載事項」をいかにうまく盛り込むかなども行政書士の重要なタスクとなります。
よって、まずは会社法の勉強をし直すことをおすすめします。
行政書士試験の受験生時代は、商法・会社法の勉強にあまり時間をかけなかったという方が多いのではないかと思いますので、なおさら会社法の勉強をし直すことが求められるはずです。
なお、一般社団法人の設立については、先述のように「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に規定がありますが、この法律については基本書ではなく条文に目を通す程度でいいでしょう。
会社法の基本書などを読み込んだ後は、①行政書士が執筆している実務書で学ぶ。②行政書士会主催の研修会を受講する。③実務セミナーを受講するなどが考えられます。
①行政書士が執筆している実務書は、行政書士の視点で書かれているのでわかりやすいと思います。ただし、書籍ということもあり、内容が薄いことがあります。興味があれば、書籍を購入して読んでみてもいいでしょう。
②行政書士会主催の研修会では、最新の実務情報を入手することができます。ただし、各都道府県の行政書士会によっては、内容や回数などに差があります。都心部の行政書士会では研修会が充実していますが、地方の行政書士会では研修会の開催そのものが少ないこともあります。
また、他の業務に比べて、法人設立業務に関する研修会の開催頻度は少ないように思います。他の業務に比べると、株式会社・合同会社・一般社団法人の設立業務の難易度がそこまで高くはないことも関係しているのかもしれません。
③実務セミナーの受講では、講師の経験に基づいた話などを事細かく聞くことができるため、すぐに実務で使える知識やノウハウなどを学ぶことができます。ただし、受講費用が高くなってしまう傾向があります。この場合、知識を学ぶのはもちろんですが、「ノウハウを買う」という視点で受講した方がいいでしょう。
ただし、行政書士登録直後の時期は実務経験がまだないでしょうし、業務経験が浅いうちは、そもそも何からどんなことを学べばよいかの判断が難しいと思われます。
そこで、代表的な3つの法人設立業務を効率よく学ぶための手順について、その例をご紹介します。
代表的な3つの法人設立業務を効率よく学ぶための手順
まずは、行政書士が相談を受ける機会が最も多い「株式会社の設立業務」からじっくり学習することをおすすめします。
そもそも相談を受ける機会が最も多い業務から先に学んでおくべきではあるのですが、株式会社の設立では合同会社の設立とは異なり、公証役場での定款認証手続も行う必要がありますので、まずは株式会社の設立からきちんと学んでおくとよいでしょう。
先に株式会社の設立業務を学んでおけば、同じ公証役場での定款認証手続が必要となる一般社団法人の設立業務を学ぶ際にも学習した知識などを活かすことができます。
行政書士実務書式セット集 株式会社設立の実務【15種類】(実務講義付き)
次に、「合同会社の設立業務」を学ぶといいでしょう。株式会社の設立に関する相談を受けた際に、相談者からよく話を聞いた結果、合同会社を設立した方が得策であると判断することもあります。また、設立費用の安さなどのメリットを知った相談者が、株式会社ではなく合同会社の設立を希望することもあります。
合同会社の場合は、公証役場での定款認証手続が不要であることで、行政書士としてはより一層「プロ」として定款を作り込む必要がありますので、株式会社の設立業務を学んだ後は合同会社の設立業務を学ぶことをおすすめします。
「合同会社の設立業務」を学ぶ実務講座
行政書士実務書式セット集 合同会社設立の実務【10種類】(実務講義付き)
そして、最後に「一般社団法人の設立業務」を学習しましょう。株式会社の設立業務で学んだ公証役場での定款認証手続に関する手順などを活かすことができます。
ただ、先述のように、一般社団法人では「設立時社員」の人数が多くなることもあるため、定款認証手続で必要となる書類の収集に時間がかかることもあります。株式会社以上に設立までのスケジュールを綿密に練っておくことが求められますので、設立までの手順だけではなく、一般社団法人の設立業務に関する注意点や落とし穴などもきちんと確認しておく必要があります。
行政書士実務書式セット集 一般社団法人設立の実務【15種類】(実務講義付き)
繰り返しにはなりますが、法人設立業務については、まずは「株式会社」「合同会社」「一般社団法人」の3つの法人形態の設立についてきちんとおさえておきましょう。
この順番での学習をおすすめしましたが、可能であれば、これら3つの設立業務についてはできるだけ短期間のうちにまとめて学習しておくとよいでしょう。そうすれば、3つの法人形態に関する基礎知識やメリット・デメリットなどを十分把握した上で、お客様に対して最適な法人形態を提案することもできますので、業務の受任率も上がってくるのではないかと思います。
「株式会社・合同会社・一般社団法人の設立業務」を3つセットで学ぶ実務講座
行政書士実務書式セット集 法人設立の実務 3点セット【39種類】(実務講義付き)
以上を学ぶことで、少なくとも法人設立業務に関する初期対応や基本的な対応を無難にこなすことが可能となるでしょう。
もしも相談者から聞かれてわからないことがあっても、「調べてから回答します。」や「特殊な案件なのですぐには回答できません。調査した後に改めて回答します。」などと一旦は回答しておくことができるようになるでしょう。
書式準備
法人設立業務を始めるにあたり、最低限初期対応のヒアリングシートと料金表は用意しておいた方がいいです。特に、定款を作成するためのヒアリングシートの作成・準備は必須です。
行政書士事務所などで働いた経験のある方であれば、その事務所の書式などを参考にしてヒアリングシートなどを作成することもできます。しかし、業務経験がない方や業務経験が浅い方は、こうした書式の準備に悩むのではないかと思います。この場合は、研修会や実務セミナーなどで入手した書式を少しずつストックしておき、自分なりに適宜アレンジしておくようにしましょう。
営業
実務の学習をして基礎知識などを身につけ、初期対応のための書式などを準備した後は、積極的に営業を行いましょう。営業方法としては、ホームページ制作、SNS、新聞・インターネット広告、DM、紹介、セミナー集客などがあります。
法人設立業務の場合は、相続業務や遺言業務などに比べるとホームページからの問合せが多い傾向にありますが、同じ行政書士からのご紹介というパターンもあります。特に、電子定款に対応していない行政書士がこれに対応している行政書士を紹介するというパターンが多く見られます。
ちなみに、紙の定款ではなく電子定款で認証手続をすると、紙の定款では発生してしまう収入印紙代4万円がかかりません。これは、お客様にとっては設立費用を抑えることにつながります。
法人設立業務の営業をする際には、収入印紙代4万円を削減することができる電子定款にも対応していることを必ず伝えるようにしてください。
受任までの流れを準備
業務を受任し、着手するまでの流れは必ず前もって決めておきましょう。
ある日突然電話で問い合わせが来たときに確認することや、面談時のヒアリング事項、設立業務の流れの説明、見積方法、受任時の契約書の準備(契約書がない場合は、見積書に条件を記載する)など、前もって決めておくべきことはたくさんあります。
まずはきちんと業務を受任することができないと、何も始まりません。当然ですが、業務を受任しなければ報酬をいただくこともできません。
受任した後のことももちろん大事ですが、まずは法人設立業務をきちんと受任できるように、前もって入念に準備しておきましょう。
情報収集
法人設立の業務に関する最新情報を入手することも大切です。最近では、令和元年に会社法が改正されましたので、改正内容についてはきちんと確認しておきましょう。また、最近は公証役場での定款認証手続に関する新制度や運用の変更などがよく見受けられますので、日本公証人連合会のホームページはきちんとチェックしておくとよいでしょう。
そして、法人設立業務を専門にしたり取扱業務の一つにしたりしている行政書士との人脈を形成し、お互い情報交換をするということも大変有意義です。同業者であれば、同じような視点から最新情報を収集していますので、かなり有意義な情報交換が常にできるのではないかと思います。何か特殊な案件があった際には、守秘義務に注意しながら仲間の先生に相談するのもいいと思います。

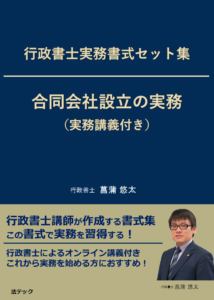

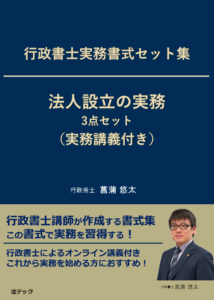


サムネイル画像320x180.jpg)